2010年05月07日
芸団協セミナー2010「海外研修サポートセミナーVol.2研修報告会『「演劇人にとって海外で研修するということ』」03/26芸能花伝舎1-1
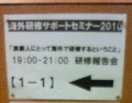
海外研修サポートセミナーVol.2
前回に続き芸団協セミナーに伺いました。ゲストは劇作家・演出家・俳優であり、劇団阿佐ヶ谷スパイダース主宰の長塚圭史さん。昨年ロンドンで約1年間(350日間)の研修をしてこられました。
研修を経て新作『アンチクロックワイズ・ワンダーランド』を発表されたばかりの長塚さんの、熱の入った力強い語り口、そして演劇を信じる言葉に勇気づけられました。大堀久美子さんのスムーズな進行のおかげもあり、2時間みっちり、とても貴重で面白いお話を聴くことができました。以下、私がメモしたことのまとめです。
■海外研修サポートセミナーVol.2研修報告会
「演劇人にとって海外で研修するということ」
ゲスト:長塚圭史(劇作家・演出家・俳優)
進行:大堀久美子(フリーエディター)
※このセミナーは札幌・仙台・大阪・広島・福岡の全国5か所でネット中継されました。東京会場以外に、70人の方が参加されていたそうです。
■ロンドンに決めた理由/ナショナルシアターStudioという恵まれた場所
長塚「研修先をロンドンに決めたのは、自分がアイルランドの作家マーティン・マクドナーの戯曲を演出したことが大きい。また、ニューヨークやパリは好きなんだけど、面白すぎるのはだめな気がして。ロンドンは暗いし曇ってるし、いい思い出もないし。自分をそういう場所に追い込むことが必要な気がしたから。それに自分がアメリカよりもイギリスの作品を好きなのもある。例えば『スウィーニー・トッド』とか。」
長塚「演出家のデイヴィッド・ファー (David Furr) がいるリリック・ハマースミス劇場に行くことになっていた。でもデイヴィッドがRSCに行ってしまったので、自分が劇場に残ることができなくなった。それでナショナルシアター(国立劇場)が受け入れてくれることに(⇒写真)。国立劇場から徒歩10分ぐらい離れた場所に国立劇場のStudio(ストゥディオ)がある。ワークショップ(以下はWSと表記)など、アイデアを膨らませる作業ために使う場所。3つの部屋があり、1週間から2週間借りて活動できる。(その恵まれた環境に)驚愕した。」
長塚「国立劇場だから寄付金を得ているのもあるのだろうけど、Studioでの活動(WSなど)に役者やスタッフが15人必要なら、15人分の最低賃金をくれるのはすごい。前線で活躍しているアーティストが次々と集まってくる、とてつもない場所だった。ウエストエンドで上演される『War Horse』(←音が鳴ります)もStudioで育てられた。」
■自分からアプローチしないと何も実現しない
長塚「国立劇場の芸術監督は演出家ニコラス・ハイトナー(Nicholas Robert Hytner)。『ミス・サイゴン』の演出家であり、映画『クルーシブル』を撮っていたりもする。僕を推薦してくれた栗山民也さんに「とにかく稽古を見ろ!」と言われていたので、彼の稽古も見学した。」
長塚「自分自身でアプローチしないと何も実現しない。「この舞台を観たい」「稽古を見たい」「部屋を借りたい」「WSをやりたい」など、何でも自分で交渉しないと進まない。もちろん英語で(笑)。」
長塚「とにかく英語ができないとだめ。制作の人からは恐ろしいほどプレッシャーをかけられた。彼らは基本的にめちゃくちゃ忙しいから厳しい。(僕の英語がおぼつかないのもあって)話している途中で無視されたりね(苦笑)。Studioにはテクニカルスタッフがいて、彼らとはとてもウマが合った。やはり制作者よりクリエイションに関わる人の方が話しやすかった。」
■自分でワークショップを開催
長塚「さぼってたらいくらでもさぼれちゃうから、自分にプレッシャーをかけていかないと。何もしないままでは馬鹿にされる。自分で何かを始めてみようと思い、1月から準備して3月にWSを開始した。」
長塚「Studioで井上ひさし作『父と暮せば』と三好十郎作『胎内』を使ってWSをやった。イギリス人の日本に対する興味は想像以上に低かった。広島は知ってても長崎は知らないとか。今の日本を語るためには、まず第二次世界大戦のことから始めないとと思っている。」
長塚「日本人とイギリス人は、まず人と人との距離感が違う。例えば日本人の僕はハグがうまくできないとか(笑)。イギリスの俳優に日本人の距離感をうまく理解してもらえないだろうかと思って、畳やちゃぶ台を用意し、日本の朝の風景のエチュード(即興演劇)などを少しずつ進めた。」
長塚「彼らはアメリカ英語がとても嫌いで、話すのを嫌がる。手に入れた『父と暮せば』の戯曲はアメリカ英語で書かれていたので、イギリス英語に直すのがまず大変。毎日1時間ぐらいその作業をした。噂にたがわぬ議論好きだから、議論はいつも長くなる。」
長塚「1週間後に発表会をした。WSでフィジカリティ(身体性)に日本の感覚を落としこんで、本番では装置をイギリスの家に全部取り換えた。『父と暮せば』の登場人物の名は“タケゾー”と“ミツエ”だが、装置も衣裳もイギリス風なので、イギリスで起こったことのように見えた。でも身体性は日本人なので、その向こうに日本が、広島が見えた。とても演劇的だった。」
■イギリスの俳優
長塚「イギリスの俳優は積極的。仕事がない時でも、いつでも勉強しているし、常に探っている。彼らは必ず万全の状態で稽古場にやってくる。芝居が生活の中に組み込まれているのが彼らのスタンス。公演のためだけに俳優をやっているわけじゃない。演出家として、俳優のそういう姿勢はとても嬉しい。」
長塚「夏に2人の俳優と3度目のWSをした。題材は2000年に書いた『侍』という一人芝居。参加者の1人ダニエル・ワイマンは今売り出し中の俳優で、年齢は僕より1つか2つ下ぐらい。彼は「テレビの仕事が終わったから何かやろう!」と言ってきた。「常に勉強」とも言っていて、電車に乗っていても「あそこにいる人の動きが面白い。あれを取り入れてみよう」など、延々と演劇の話をするタイプ。」
長塚「アマンダ・ローレンスという女優は、休みの日に女優を集めてリーデイングをやっている。勉強のために。僕が住んでいたアパートにいたおばあちゃんも、何人かで集まってストーリーテリングの勉強会をやっていた。そうやって常に練習している。」
■イギリスの制作者・劇場関係者
長塚「ゲートシアター(ザ・スズナリより小さい劇場)で『ワーニャ叔父さん』を観た。そこの芸術監督は26~7歳のとても若いナタリーという女性。寄付金を集めたり、しっかり運営していた。」
長塚「バタシーアートセンター(Battersea Arts Centre)という元市庁舎だった建物。300部屋もあり、アーティストの交流が激しい。そこの芸術監督(Artistic Director of BAC in London)であるデイヴィッド・ジョブ(David Jubb)は、劇場をいかに素晴らしい空間にするかに興味を持っていた。プログラムを決める芸術監督というよりは、人と人とをつなげて最高の出会いをさせて、育てていくことに興味がある。つまり商業的なものとは正反対。」
■イギリスの劇場
長塚「イギリスの劇場の在り方に感銘を受けた。それぞれの劇場が熱くて(熱気があって)、人々が交流できる場所だった。夏には野外フェスティバルがあり、観客じゃない人もいっぱい集まっている。常にコンサートが開かれていたり、若い人が新しいことを試していたり。国立劇場ではいつも新しいものが生まれ、上演されているし、電光掲示板で今やってる演目を宣伝している。情報の発信の仕方が日本とは全然違う。」
長塚「芸術監督のニコラス・ハイトナーは「(国立劇場は)国民のための最大のマーケットでありたい」と言っていた。彼は新作も古典もどんどん演出している。彼が演出したイギリスの移民の歴史をひもといた作品は、色んな民族をひどく悪く言う芝居で(笑)、劇場にはものすごい苦情が来た。でも彼は常に攻めの姿勢だった。彼は「劇場が強くあれば演劇は育つ」と思っている。自分の理論を持っている。芸術監督は名誉もあるが大変な仕事。」
長塚「“劇場が強くあること”“そこに人が集まること”。僕はいい場所で作品を作っていきたいし、日本のプロデューサーや劇場関係者に、演劇を文化としてとらえる熱意があればいいなと思いました。」
↑Royal National Theatre, London from Waterloo Bridge 劇場公式サイトより。
■帰国後の新作『アンチクロックワイズ・ワンダーランド』
長塚「“帰国後第一作目”とかプレッシャーをかけられて、すごく嫌だった(笑)。そうするとますます不親切なことを、凶暴な形でやりたくなってしまうんですよね。」
長塚「『アンチクロックワイズ…』は物語を書くことに興味を失ってしまった1人の作家の話。書き手として僕はストーリー・テリングが好きな分、次から次に現代の新しい物語を作ろうとしてきたけれど、どこか物足りなさを感じていた。時間や存在について考え始めていた。」
長塚「思い切って今回は演出部(のスタッフ)なしで稽古をした(不況というのもあったけど)。俳優が演技もし、セットも動かした。片付けるのも俳優。本番が近くなってから、俳優が演出部にセットの動かし方を教えた。そうすると演出部のヤル気もすごく増す。僕はスタッフも限りなく作品の一部だと思っている。」
■「本当に僕は演劇が豊かだと思う」
長塚「舞台を観る時は、観客も舞台に参加しなきゃいけないんじゃないかと思って。これは悪くない考えだと思う。良い悪いに関係なく、舞台から何かをもらうのだから。劇場において、観客とともに、観客なしには成立しない演劇を作りたい。」
長塚「ペットボトルの水を手に持って“これが妻です”と言ったら、それが成立してしまうのが、演劇。本当に僕は演劇が豊かだと思う。何もないところから作り上げられるのだから。そこに一度、大きく立ち戻れたことが良かった。観客にはその(演劇の虚構を受けとめる)準備ができているはず。そこに面白さを感じる。」
長塚「幸い僕は(日本の)大きな劇場で作品を作ったり、素晴らしい体験をさせてもらった。今後もエンタメをやりたい気持ちはある。でも忙しくなると見えなくなることもある(忙しい時:「もっとくれ!もっとくれ!」と言われ続けてるような、周囲の要求に歯止めが利かない状態。)。演劇とは何だろうと考えながらやっていきたい。常に原点に戻って作り上げていく。そこを怠らずに芝居に向かっていきたいと思った。」
■これからの劇場・プロデューサーについて
長塚「僕が研修に行ったのが国立劇場だったのもあって、「日本の国立劇場はどうなの?」って尋ねられるんですよね。日本の国立劇場というと新国立劇場なんですが、僕はもっと宣伝をして欲しいです。新国立劇場でやる演劇はちゃんと値段も高くないし、もっと多くの人が来てほしい。最近、鵜山仁さんが僕と同世代の若い人たちと色々やったりしていました。日本の演劇を観に、年齢問わず人が集まる場所にしてほしい。」
長塚「例えば野田秀樹さんが芸術監督になった東京芸術劇場など、最近は新しい試みにあふれていていいと思う。劇場同士がお互いに強い刺激を受ければいいし、そしていいコネクションを作っていけばいいんじゃないか。そこからさらに上へ、上へと活動していけば、地域も活性化すると思う。若い演劇人が芸術監督になって、活動の中心に立って盛り上げていけばいい。きっと面白くなるだろう。あせらずに、意識しながら現状を変えていってほしい。」
長塚「これは僕の勝手な意見ですけど、日本の映画の才能や歌舞伎の才能が演劇で交わり、その公演に山ほど客が入った時代はもう終焉を迎えると思う。今はいい時期に入ってきている。プロデューサーの人たちは、そのいい時期を逃さないでほしい。有名俳優が出てるスター・システムも大事だけれど、“色んなキャスト・スタッフを集めてカンパニーを置きました(座組みを作りました)”というところで終わらないで、そこから何を見せるかに突っ込んでいってほしい。」
長塚「難しいことだけれど、まず、どの作品をどういう風にやるのかを徹底的に話して、そこから作品を作りはじめる座組み(がいいと思う)。そのためには1つ2つ、早めに手を打たないとだめだけど。プロデューサーは作る段階に関わって、そういうことを、きちんとしていかないといけないんじゃないか。」
長塚「あわただしい日本の芝居の作り方も、それはそれで好きだし、否定する気もない。でも弱い企画や危い公演も多い。制作者が厳しい気持ちを持って欲しい。はっきりとした意見を交換できないプロデューサーだと、芝居の世界が豊かになるのに時間がかかるのではないかと思う。」
長塚「劇場に交流の場が欲しい。人がワッと集まれる空間があるといい。ロンドンの劇場もそうだし、ベルリンもそう。多くの劇場関係者がそのように思ってくれたらいいなと思います。」
※「プロデューサー」と「制作者」について。名称は違うものの、ここでは同じ仕事を指していると思います。
■留学中の具体的な収穫例
・戯曲
長塚「仕入れてきた戯曲をパルコ劇場でリーディング上演します。『ビリー・エリオット』というミュージカルをつくった、リー・ホールという劇作家の一人芝居。」⇒2010年4月上演『スプーンフェイス・スタインバーグ』
・子供のための演劇
長塚「3歳までの子供ための芝居を観ました。感激しますね。僕が観たのは“地球を作っていく”ことを表現した作品。見る力、想像力を徹底的に考えたつくりになっていて、大人も楽しめるものだった。質の高い作品が地方の小さなところで上演されている。子供のころから、いかに演劇がそばにあるのかがわかる。」
■これから留学される方へのアドバイス
長塚「イギリスに行くなら英語!僕はとにかく英語に苦労しました。英会話学校でネイティブの先生に習っていて、「お前の英語は大丈夫だ」と言われたのに、いざロンドンでおばさんに道を尋ねてみたら、そのおばさんの英語が全く聴き取れなかった(苦笑)。クイーンズ・イングリッシュじゃないとだめなんですよね。」
長塚「“1年”という期間を意識しない方がいい。自分からリミットを数えてしまうから。向こうの人間は当然ながら、そんなこと全然考えずに接してくる。意識し過ぎるとあわててしまい、からまわりしちゃう可能性がある。だからあせりすぎないで、ドンとかまえていた方がいい。自分の興味は移り変わるものだから、それ(移り変わる興味)に乗っかっていった方が面白いに決まってる。」
ネット中継:札幌・仙台・大阪・広島・福岡 3月26日(金)19:00-21:00
ゲスト:長塚圭史(劇作家・演出家・俳優 阿佐ヶ谷スパイダース主宰)/平成20年度文化庁新進芸術家海外留学研修員としてロンドンで研修 進行:大堀久美子(フリーエディター) 司会:米屋尚子(芸団協)
主催:社団法人日本芸能実演家団体協議会 共催:社団法人日本照明家協会 /日本舞台美術家協会(vol.1) 社団法人日本劇団協議会 (vol.2) 協力:文化庁芸術家在外研修員の会/NPO法人FPAP Arts Managers' Net 広報協力:社団法人日本劇団協議会/日本舞台音響家協会/日本舞台監督協会(いずれもVol1.) 助成:平成21年度文化庁芸術団体人材育成支援事業 社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
参加費2,000円(茶菓代を含む。) 事前に必ずお申込みください。
http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/04pro/manage/kaigai10vol12.html
http://www.fpap.jp/netseminar/2010/
※クレジットはわかる範囲で載せています。正確な情報は公式サイト等でご確認ください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
★“しのぶの演劇レビュー”TOPページはこちらです。
便利な無料メルマガも発行しております。
世田谷パブリックシアター『日本語を読む その3~ドラマ・リーディング形式 による上演~「熱帯樹」』05/05-08シアタートラム
シアタートラムでのリーディング公演です。毎年5月のお約束になってきました。今年も若手演出家が3人取り上げられ、キャストが豪華です。1000円はお得!
トップバッターの谷賢一さんが演出される三島由紀夫戯曲『熱帯樹』を拝見。リーディングなのに2時間40分(途中休憩10分を含む)という大作でした。エロティックで濃厚で良かった~。
⇒History of 『日本語を読む』
⇒稽古場写真
⇒CoRich舞台芸術!『熱帯樹』
レビューは記録程度です。
≪設定≫
父(吉見一豊)、母(久世星佳)、兄(石母田史朗)、妹(中村美貴)の4人家族、そしておば(松浦佐知子)が暮らす家。
≪ここまで≫
官能的な部分が強調されていてとても面白かったです。特に母と兄のやりとりにはゾクゾクしました。
★「老花夜想(ノクターン)」のレビューより↓
私の戯曲の好みもあると思いますが、3つの中では『熱帯樹』が断トツに面白かったですね。発語の方法(声の大きさ、早さ、抑揚など)を工夫し、戯曲の独自の解釈にもとづいて、言葉の色、深み、味わいを作り出していました。照明、音響、選曲についても一番凝っていたように思います。何より登場人物が恐ろしい怪物のように(見たことのない巨大な熱帯樹のように)見えたことが、私にはすごく良かったです。あ、『熱帯樹』の感想になっちゃいました。
≪ポスト・パフォーマンス・トーク≫ 記録程度です。
出演:プロデューサーの楫屋一之さん、演出の谷賢一さん
谷「この戯曲には三島の性や死に対する美学が凝縮されている。」
谷「(演出についての問いに答えて)エッチにしたいなと思った。」
谷「昭和の文豪の文体には英語的なところがある気がする。明治の夏目漱石や二葉亭四迷だとむしろ江戸時代風で、たとえば落語のような言い回しがあったりする。でも昭和になると西洋文学の要素(メタファー、隠喩、比ゆなど)を、日本語の美しさに落とし込んでいる、そんな要素があるのではないか。」
出演:石母田史朗/久世星佳/中村美貴/松浦佐知子/吉見一豊
脚本:三島由紀夫 演出:谷賢一(DULL-COLORED POP) 舞台監督:鈴木章友 照明プラン:三谷恵子 照明操作:大屋惠一 音響プラン:小笠原康雅 音響操作:中田摩利子 遠藤瑶子 プロダクションマネージャー:福田純平 道具製作:水森利明 衣裳:三茶小町 小道具協力:高津映画装飾株式会社 法務アドバイザー:福井建策 営業:鶴巻智恵子 吉兼恵利 広報:宮村恵子 和久井彩 武井美津子 制作進行:相見真紀 制作:穂坂智恵子 矢作勝義 大下玲美 菅原力 内田安紗子 [主催] 財団法人せたがや文化財団 [企画制作] 世田谷パブリックシアター
【休演日】5/6,7【発売日】2010/04/04 一般 各作品1,000円 高校生以下500円(劇場チケットセンターのみ取扱い、年齢の確認できるもの要提示) TSSS 500円
http://setagaya-pt.jp/theater_info/2010/05/3_1.html
ゴジゲン『アメリカン家族』04/29-05/02吉祥寺シアター
ゴジゲンは松居大悟さんが作・演出・出演される劇団です。劇団といっても所属しているのは松居さんと俳優の目次立樹さん、プロデューサー、制作のみですので、プロデュース団体といっていいかもしれませんね。
「CoRich舞台芸術まつり!2010春」審査員として拝見しました(⇒91本中の10本に選出 ⇒応募内容)。※レビューはCoRich舞台芸術!に書きます
⇒CoRich舞台芸術!『アメリカン家族』
≪あらすじ≫ 公式サイトより
朝起きたら母がいなくなっていた。
父は何も言わずにビチョビチョのご飯を出して、ボクは息を止めて全部食べた。
もう家には嫌いな人しかいない。
唯一の救いは、互いに嫌い合っていることを全員がわかっているということだ。
そんな気まずい空気の中、目の前に広げられた小粋なケーキや素敵なプレゼント。
ボクはずっと床の木目を見つめていた。
祝う気なんかないクセに。
こうして誰からも望まれない誕生日パーティーが始まった。
バラバラの家族が取り繕う、バレバレの一家団欒。
家族なんだけど!いつか殺す!!
最低な善意が暴走する、救いようのないホームコメディ。
凍りついてこそ家族だ。
≪ここまで≫
第8回公演
出演:安藤聖 奥村徹也 加賀田浩二(飛ぶ劇場) 島田曜蔵(青年団) 津村知与支(モダンスイマーズ) 土佐和成(ヨーロッパ企画) 東迎昂史郎 松居大悟 目次立樹 吉牟田眞奈(THE SHAMPOO HAT)
脚本・演出:松居大悟 舞台監督 / 川除学+至福団 舞台美術 / 片平圭衣子 小道具:高津映画装飾 照明 / 伊藤孝(ART CORE) 照明操作 / 上原皓介 音響 / 鏑木知宏+角田里枝 音楽 / 森優太 映像 / 大見康裕 衣裳 / 本間圭一 横田真理 演出助手 / 久保大輔 演出補佐 / 青木直也 西岡知美(カミナリフラッシュバックス) 演出部:上嶋倫子 宣伝美術 / 今城加奈子 WEB / 飯塚美江 後輩 / 橋爪知博 制作 / 半田桃子 武藤香織 プロデューサー / 北川隆来 企画製作 / ゴジゲン
【発売日】2010/03/20 前売り3,000円、当日3,500円、学割2,000円
http://www.5-jigen.com/
「CoRich舞台芸術まつり!2010春」最終選考作品
http://stage.corich.jp/festival2010/detail.php?stage_main_id=10216
※クレジットはわかる範囲で載せています。正確な情報は公式サイト等でご確認ください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
★“しのぶの演劇レビュー”TOPページはこちらです。
便利な無料メルマガも発行しております。


